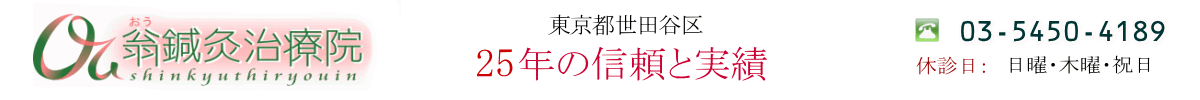痔
痔と鍼灸治療
当院では痔の鍼灸治療を積極的に行われており、良い効果が得られています。痔の鍼灸治療は手術する前に是非試してみてください。痔の症状が軽い場合は手術しなくても鍼治療で済むことが結構多いです。鍼灸の効果が期待できるのは痔核と裂肛になります。鍼とお灸で局所の循環を改善することを中心に、便秘であればその治療も併せ、ストレスがあればそれを取り除くよう、全体的に診ていきます。直接的な原因としては肛門周辺の毛細血管に血流障害があります。静脈がほそく網の目状に細かくなっているので血流が滞りやすく、また位置的に骨盤内にあるので腹圧や妊娠などによる負荷がかかりやすいことが要因となります。 便秘が引き金になることも多く、元をたどると食事内容やストレスも関係しています。
痔について
痔とは
肛門やその周辺に起こる病気の総称です。日本人の3人に1人は痔であると言われるたいへん身近な病気のひとつです。直立歩行をする私たち人間は、おしりが心臓よりも低い位置にあるためうっ血しやすく、もともと痔になりやすいのです。痔になりやすいことに加え、トイレで強くいきむ、辛い食べ物など刺激物を食べる、長時間座りっぱなしの仕事をしているなど、おしりに負担のかかる食生活や生活習慣が痔の発症や症状の悪化に大きく影響します。
痔の種類
①痔核
いわゆるイボ痔のことで、直腸の方にできる内痔核とそれが進行すると肛門の外に出てしまう外痔核があります。排便時に便器に滴るような出血を伴うことがあります。外痔核になっても初期であれば直腸のほうに収まりますが慢性化すると指で押しても戻らなくなります。
②裂肛
いわゆる切れ痔のことで、便秘のためいきむ時間が長く肛門部に過剰に負荷がかかることや、便が腸内に滞っているため水分が奪われてしまい硬い状態で肛門を通過するので、肛門の粘膜が傷つけられて強い痛みと出血を引き起こします。切れた部分は排便時にまた切れやすく痛むので、排便自体を我慢して便がさらに硬くなり、進行すると傷口部分が潰瘍化します。
③痔ろう
あな痔とも言います。肛門部を便が通過する時、特に下痢においては肛門腺から大腸菌などが細菌感染して化膿する場合があり、化膿が進行するとトンネルが形成され、それが肛門の周囲や直腸に開口し膿が排出されることがあります。膿み・腫れ・痛み・発熱を繰り返し、化膿の範囲が広がると人工肛門となる場合があります。
痔の主な治療法
- お薬による保存療法
- 保存療法で治らなかった時は病院で硬化療法やゴム輪結紮療法を行います
- 肛門から脱出しているときは、手術を行います
- 退院後も再発しないよう養生します
- 鍼灸と併用したりするとよいでしょう。
痔の生活療予防法
原因となる生活習慣を改善すること。痔が治ってからも、再発を防ぐために、生活習慣に気をつけましょう。
- 便秘をしないように気をつける
- トイレで強く力まないように
- 毎日お風呂に入る
- 長時間の座りっぱなし、立ちっぱなしはやめる
- 腰を冷やさないようにする>
- 食物繊維や水分をしっかりとる
- ストレスをため込まないようにする>
- おしり洗浄器付きのトイレの利用
翁鍼灸治療院へのアクセス
鍼灸院の住所は東京都世田谷区経堂2丁目3ー1 木津ビル 4F小田急線経堂駅北口から徒歩30秒です。治療院は四階で一階はケンタッキーフライドチキンです。
電車ご利用のかたへ:
新宿から小田急線で急行12分 ・ 準急・各駅停車12~20分です。
平日の夕方18時以降(下り)小田原方向への急行は経堂駅に停車しませんのでご注意ください
車でお越しのかたへ:
当院には駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングなどをご利用ください。
ご予約とご相談はこちらへ
当鍼灸院は完全予約制となっております。
TEL・ FAX: 03-5450-4189
ご質問・ご予約のメールフォーム
(お急ぎお方は電話にてご予約ください)